駒澤大学経営学部教授 青木茂樹
【理論と実践のブランド論 第5回<最終回>】

論文や著書、コラムなど積極的に知見を発表する一方で、自らNPOを立ち上げ、理事長として地域活性に取り組む青木氏。「NPO法人やまなしサイクルプロジェクト」のイベントは1000人以上を集める大きなうねりに成長している。その裏側には自らが提唱する「クロス・バリューチェーン」を軸とした「サステナブル・ブランディング」という確固たる理論があった。教授でありながら理論と実践を体現する青木氏に、その意図、背景、そしてブランド論についてたっぷりと話を聴いた。
聴き手・構成:BRAND THINKIKNG編集部 撮影:落合陽城
海外のローカル・ブランドに負けるな。
(編集部:前回、企業の大義であるビジョンやミッションの存在が今後は強く問われ、それがサステナブル・ブランドへとつながるという話になりました。)
——–今後は日本の小さなブランドが海外へ出ていく可能性があるとのことでしたが、なかなか日本企業の海外進出は進みません。
例えば、タイは数年前から観光に力を入れていて、スパ&リゾートということで、街中にマッサージ店がいくつもできました。ビーチに行けば、まさに高級リゾート。昔とはイメージがガラリとかわりました。その流れの中でタイからは「TAHHN」という高級化粧品が出てきています。日本でも7店舗あり、表参道や銀座、六本木などに店舗を構えています。このブランドは動物実験しません、とか児童労働しませんとか、ナチュラルな素材をつかいますとか、グローバルなスタンダードをしっかり謳っているんですね。それで世界へどんどん進出していきました。中国では高級なシルク製品「ANNABEL LEE」が出てきています。それまで中国のシルクは粗悪だったし、龍の刺繍とか入っていたりして、誰も買いたくなかった(笑)。それを変えましたね。アジアの若者は海外へどんどん留学して、異なる価値観を吸収しています。そういう人たちが自分の国に戻って、新しい考え方でやっているのではないでしょうか。多くの日本のローカル企業だと、海外へ視察へ行っても、補助金で行くことが多いから、そこからリスクを取ってない。ぜひ若い世代に期待したいですね。
自分たちのヒストリーを大切にすべき。
——–日本発の注目ブランドはありますか。
山梨県にある近藤ニットが仕掛けている「evam eva」。大手企業の下請けではなく、本当にいい上質なニットを届けようと頑張っています。お客様を裏切ることになるのでバーゲンは一切しないし、数量も限定。きっと近いうちに世界へ出ていくのではないでしょうか。こういう元気なローカル・ブランドに共通するのは、自分たちのヒストリーを大事にしていることです。量産型のブランドにはない視点です。例えばそれはInstagramにも現れます。ツール・ド・富士川を開催した時、自転車の写真もさることながら、風景や食べ物などの写真が多くアップされました。通常のレースだと自転車の写真にところが、まったくそうではなかったんですね。山梨県甲州市の勝沼醸造さんの公式Instagramも、ワインだけでなく、ぶどう畑や醸造酒、会食の風景などさまざまな体験を掲載しています。大企業ができない、細かなネットーワークの構築こそ、ローカル・ブランドが成長していく上での源泉になります。
 図版作成:青木茂樹
図版作成:青木茂樹
永く愛されるブランドをつくる方法。
——–青木教授の提唱する「サステナブル・ブランディング」の4Pはブランド論の本質そのものだと思います。
サステナブル・ブランディングとは、「大義(cause)があり、社会性や地域を巻き込んだブランドづくり」と定義しています。それを叶えるには4つのPがあると考えていて、存在意義(Purpose)、差別化(Positioning)、連携(Partnering)、称賛(Praised)の4つと分類しています。これまでは「あるべき姿」と言ったときに、とかくCSR的な分野で議論がなされることが多かったと思います。また日本は部署による縦割り意識が強く、組織のヨコの連携が機能しない嫌いがあったと思います。しかし成熟した、競争の激しい社会では、世の中により貢献するという意識がないと、選ばれるブランドにはなりにくいでしょう。よく似た概念として、ポーターの提唱したCSV(Creating Shared Value)とも近いですが、CSVはやはり一企業から見た垂直構造型です。例えばコーヒーメーカーがコーヒー農園をサポートすることなどがそれに当たります。サステナブル・ブランディングは、ユーザーも、自治体も、地元企業も地域の連携を活かしたり、本当の生活者の課題解決のためにオムニチャネルを創造する「クロス・バリュー」の視点。その土地の価値が、ブランドになり得るという発想です。これを実践しているのが、やまなしサイクルプロジェクト。山梨に自転車文化が根付いて、いろんな企業が参入することで地域が活性化すれば、NPOとしてこんなにうれしいことはありません。
 やまなしサイクルプロジェクト主催「南アルプスロングライド」のスタート前。/写真提供:やまなしサイクルプロジェクト
やまなしサイクルプロジェクト主催「南アルプスロングライド」のスタート前。/写真提供:やまなしサイクルプロジェクト
(おわり)




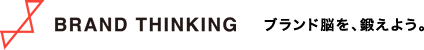
































※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して弊社は一切の責任を負いません。